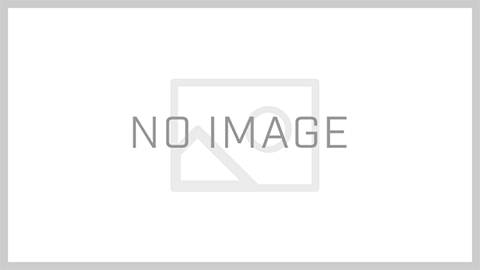世界遺産 平等院 情報
住所:京都府宇治市宇治蓮華116
TEL :0774-21-2861
拝観料:庭園+平等院ミュージアム鳳翔館
大人:600円
中高生:400円
小学生:300円
- 京都駅からJR奈良線 宇治駅から徒歩10分
- 京阪電車「宇治線」宇治駅から徒歩10分
平等院見どころまとめ
平等院見どころ1:鳳凰堂

国宝
平安時代(天喜元年)
天喜元年(1053)に建立された平等院の中心となる建物である。
本来の名称は本尊定朝(じょうちょう)作阿弥陀如来坐像を安置する阿弥陀堂であるが、屋根上に風風の棟飾があることから江戸時代より風風堂の名で呼ばれ、今ではこの名称がすっかり定着している。
構造的には中堂·両翼廊(よくろう)·尾廊(ぴろう)の4棟からなる。
中堂は桁行3間、梁間2間で一重裳階(もこし)付き入母屋造(いりもやづくり)。
両翼廊は両隅で前方に折れ曲がり、延長の桁行8間、梁間1間。
隅楼(すみろう)は二重三階宝形(ほうぎょう)造で切妻(きりづま)造。
廊は一重二階で切妻造。
中堂の後ろに伸びる尾廊は桁行7間、梁間1間で一重切妻造。
いずれも本瓦葺である。
平等院見どころ2:鳳風堂中堂前石灯龍
花尚岩製竿から上:鎌倉時代
基台:平安時代
総高202.0cm風風堂中堂の前に置かれた六角石灯篭で、火袋(ひぶくろ)部分は2石を立て、円筒形の竿と円形蓮華座(れんげざ)の基台を持つが、これらは当初からの姿ではない。
もとは基台の上に金銅の灯篭を載せたいわゆる置灯篭であったらしく、竿から上の部分は後に補われたものである。
かつて平等院型としてこの灯篭の写しが造られた。
今では鳳風堂の中堂前になくてはならない一風景となっている。
平等院見どころ3:鳳風堂 北翼廊·反橋·平橋
風風堂に北から入堂する際に渡る二つの橋である。
中に小島を挟んで平橋と反橋が架けられている。
風風堂に北から渡る橋が二つあったことは寺に残る古図などにも記されており、このたびの庭園整備の中で復興されて旧観を取り戻した。
平等院見どころ4:鳳風堂正面洲浜
平成2年(1990)から13年間かけて行なわれた史跡名勝「平等院庭園」整備事業による発掘調査によって、風風堂のある中島や対岸の打(みぎわ)から、平安時代浄土庭園の特徴である拳(こぶし)大の河原の玉石を敷き詰めた洲浜(すはま)が確認され、当初の姿に復元された。
平等院見どころ4:鳳風
銅鋳·鍛製銭金
身高(南) 98.8cm
国宝
平安時代
(北) 95.0cm
風風堂の中堂の両隅の屋根の上には、中国で想像上の瑞鳥とされる金銅製の風風一対が相対して置かれている。
くちばしと眼光は鋭く、両翼を左右に強く広げ、雄々しく胸を張った姿はいかにも猛々しい。
頭·胴体·翼·脚を別鋳とし銅板製の風切羽や尾羽を鋲(びょう)留めとする。
本尊阿弥陀如来坐像を制作した定朝が風風の木型を造ったとされる。
平等院見どころ5:鳳風堂 中堂·尾廊南面
正面からでは見えないが、鳳風が翼を左右に広げて長く背後に尾を伸ばしたように、鳳風堂は左右の翼廊と、背後に尾廊を持つ。
翼廊は通路としての意味を持ち、低い上層階は実用的ではないが、尾廊は人が立ち振る舞うに十分な広さと高さがあり、儀式の際の控えとして用いられたのであろう。
平等院見どころ6:阿弥陀知来坐像·雲中供養菩薩像と天蓋
ともに国宝
阿弥陀如来:像高278.8cm
雲中供養菩薩:
総高40.0~87.0cm
像高33.6~65.4cm
天蓋:円蓋径293.6cm
方蓋幅486.6cm
阿弥陀如来坐像の背後には大光背(こうはい)が覆い、さらにその上には方蓋(ほうがい)と円蓋(えんがい)とが荘厳(しょうごん)する。
方蓋は探漆螺細(きゅうしつらでん)、円蓋は宝相華透彫りで装飾されている。
四方の長押(なげし)の上には雲中供養著薩像52躯が楽器を奏でながら楽しそうに飛来している。
相好(そうごう)円満でゆったりとした体堀の阿弥陀如来像で、「非の打ち所がない」という言葉は、まさに平等院の阿弥陀如来のためにあるのかと思うほどである。
平等院見どころ7:観音堂
重文
鎌倉時代
平等院北門から入って左手にあるのが、重要文化財の十一面観音菩薩立像を安置していた観音堂である。
宇治川に臨む釣殿(つりどの)につながる本堂の跡地に、鎌倉時代になって建立されたもので、別名釣殿ともいう。
二軒(ふたのき)の地垂木(じだるき)が楕円形になり、内部は四周1間を外陣 (げじん)とし、中央に入組み天井を持つ内陣とする。
須弥壇を3間に分かち、中央に厨子入りの本尊十一面観音菩薩立像、向かって右に不動明王立像二童子像、左に地蔵菩薩立像を安置していた。
桁行7間、梁間4間、重寄棟造、本瓦で、典型的な中世密教仏堂建築の特色をよくしめしている。