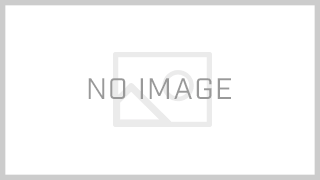萬福寺 情報
住所:京都府宇治市五ケ庄三番割34
TEL :0774-32-3900
拝観時間:9:00 ~ 17:00(受付は16:30まで)
拝観料:
| 種別 | 個人 | 団体(30名以上) |
|---|---|---|
| 大人 | 500円 | 450円 |
| 大学生・高校生 | 500円 | 300円 |
| 中学生 | 300円 | 250円 |
| 小学生 | 300円 | 200円 |
アクセス:
- JR奈良線「黄檗駅」下車 徒歩5分
- 京阪宇治線「黄檗駅」下車 徒歩5分
萬福寺見どころまとめ
永観堂禅林寺見どころ1:総門

江戸時代(元禄6年)
重要文化財
蔦福寺総門の前に立つと、いかにもこれから中国風の禅院に足を踏み入れる、の感がある。
中央を一段高くし、左右を一段低くした、いわゆる牌楼(ぱいろう)式の門で、漢門ともいわれる。
屋根の両端には摩伽羅(まから)と呼ばれる、インドにおける想像上の動物が置かれる。
わが国の熊(しゃち)に似るが、鰭(ひれ)ではなく脚が付いており、ガンジス川に生息するというインドの女神の乗り物とされるワニに原型があるという。
水辺での最強の動物であることから、聖域結界の象徴として記られる。
萬福寺見どころ2:三門
重要文化財
江戸時代(延宝6年)
総門を入って石条(せきじょう)と呼ばれる独特の石敷きの参道に沿って行くと、 重層で楼門造の三門が見える。
3間3戸、左右に裳階 (もこし)と山廊(さんろう)がある。
禅宗にとって三門とは、煩悩を離れた三解脱門の意で、これから先は脱俗の清浄域に入ることをあらわす。
正面上層及び下層にはともに隠元禅師の筆になる「黄巣山」、「菖福寺」の届額が掲げられる。
また背面には千呆(せんがい)の筆になる「梅檀林(せんだんりん)」の額が掲げられる。
延宝6年(1678)に横田道補信士の助縁になる。
萬福寺見どころ3:法堂
江戸時代(寛文2年)
重要文化財
大雄宝殿(だいおうほうでん)からさらに石条 (せきじょう)を進むと、 法堂 (はっとう)がある。
住持が衆僧に説法をもっぱらにする場で、他の臨済寺院と違い、須弥壇(しゅみだん)はあるが仏像は安置されていない。
桁行5間、 梁間6間、一重入母屋造(いりもやづくり)、桟瓦葺で、 正面には費隠筆の「獅子帆 (ししく)」の額が掛かる。
獅子乳とは、 釈迦が説法すると、獅子が砲呪して百獣を怯えさせるほどの威力があるとの警(たと)えから付けられたという。
内部には須弥壇があり、その上方には隠元禅師の筆になる「法堂」と大書された額が掲げられる。
萬福寺見どころ4:出くずしの勾欄
江戸時代
開山堂正面と同じく法堂正面の勾欄は、己くずしの文様になっている。
わが国では法隆寺の金堂や五重塔に「己崩し勾欄」の先例を見ることが出来るが、他に例がない。
己をモチーフにした勾欄は中国明代禅宗寺院の建築様式の影響を強く受けたものである。
萬福寺見どころ4:天王殿
重要文化財
江戸時代(寛文8年)
三門を真っ直ぐに進むと一山の玄関ともいうべき天王殿がある。
天王殿とはチベット仏教寺院に由来し元王朝によって中国にもたらされ、中国式の禅宗寺院に定着したものであるが、日本では黄業宗寺院のみに見られるものである。
内陣正面に弥勤菩薩の化身とされる布袋坐像が泥られ、その背面には大雄宝殿の釈迦如来と対面するかのように、護法善神としての車駄天(いだてん)像が安置されている。
また四方には守護神としての四天王が配されている。
桁行5間、梁関3間、一重入母屋造本瓦葺で、旧葺板の墨書銘から寛文8年(1668)の建立になることが分かる。
萬福寺見どころ5:祖師堂
重要文化財
江戸時代(寛文9年)
花道生(はんどうせい)の制作になる禅宗初祖の達磨大師坐像と、開山隠元禅師から59代までの歴代住持の位牌を配っている。
梁銘により寛文9年(1669)に今津浄水道源居士の喜捨
によって建てられたものであることが知られる。
桁行梁間3間、一重入母屋造、本瓦葺。
萬福寺見どころ6:禅堂
重要文化財
江戸時代(寛文3年)
大雄宝殿(だいおうほうでん)に向かって左手にある桁行5間、梁間6問、一重入母屋造、本瓦年の建物で、本尊白衣(ぴゃくえ)観音坐像、脇侍に53人の善知識を歴訪したという善財童子(ぜんざいどうじ)、及び文殊(もんじゅ)菩薩の教化を受けて即身成仏したという八蔵龍女(はっさいりゅうじょ)を配る。
正面に掲げられた「選俳場」の額は、隠元禅師の書になるものである。
ここでは坐禅を行う場所となっている。
内部は三尊を挟んで東西に別れ、衆僧は東単に、俊寮などの外寮は西単に対面して坐禅をする。
萬福寺見どころ7:大雄宝殿
江戸時代(寛文8年)
重要文化財
高福寺伽藍の中心に位置する最も大きな建造物で、禅宗寺院における本堂にあたる。
桁行3間、 梁間3間、一重裳階(もこし)付、 入母屋造、本瓦葺。
上層正面に隠元書になる「大雄賓殿(だいおうほうでん)」、下層に木庵書になる「菖徳尊」の扇額が掛かる。
堂正面は石垣で一段高くなっており、月台(げったい)と呼ばれる白砂が一面に敷き詰められている。
常に月光を受けるが故に名付けられたという。
月台の中央には戒を破った僧を置いて懲らしめるために、楚壇石(ぼんだんせき)が一枚置かれている。
萬福寺見どころ8:開梯 斎堂での開梯·雲版
斎堂(さいどう、重要文化財、江戸時代 [寛文8年])は大雄宝殿に向かって右側にある。
菖福寺の衆僧が食事をする場所で、内部には緊那羅王(きんならおう)菩薩を泥り、中国風に食事をするために高脚の飯台と腰掛が並ぶ。
桁行5間、梁間6間で、一重入母屋造、本瓦葺の建物で隠元禅師在生中の寛文8年(1668)の建立になる。
堂の表には、鬼界の衆生(しゅじょう)に施与する飯を載せるための生飯台(さばだい)がある。
堂前には日常の行事の刻限を知らせる魚の形をした開梯(かいぱん)と雲版(うんぱん)が掛かり、菖福寺の伽藍に無くては
ならない景物となっている。
開梯は叢林(そうりん)における日常の行事や儀式の時刻を修行僧が開桃を礼棒で叩き報じる。
また雲を倣った雲版は、食事や朝課の時刻を知らせるために打ち鳴らす。
萬福寺見どころ8:松陰堂
重要文化財
江戸時代(寛文3年)
開山堂に向かって右手にある建物で、寛文3年(1663)に庵として建立された。
ほかの多くの建物が中国様であるのに対して、松隠堂は書院風の和様となっている。
隠元禅師は翌4年に薦福寺住持を退いて、寛文13年に示寂するまで9年をここに過ごした。
寂後もとは客殿であったが、元禄時代に現在地に移築された。