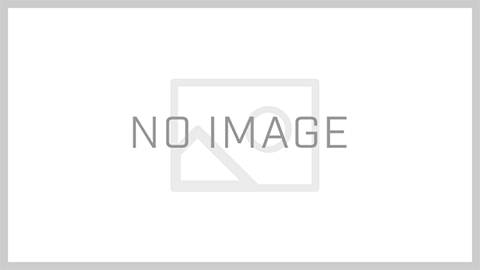南禅寺 情報
TEL:075-771-0365
宗派:臨済宗大本山
拝観:境内自由 方丈庭園:400円 三門:400円 南禅院:250円
交通:京都市地下鉄 蹴上駅 徒歩約10分
南禅寺見どころまとめ
南禅寺見どころ1:三門

重要文化財
江戸時代(寛永5年)
南禅寺の中門を入ってひときわ目に付くのが三門である.5間3戸2階二重門で、入母屋造(いりもやづくり)本瓦葺、両袖に昇降のための山廊が付属している。
この三門は寛永5年(1628)に伊賀国(三重県)の大名藤堂高虎(とうどうたかとら)の発願になるもので、慶長19年(1614)の大坂夏の陣で戦死した家来たちへの供養のために寄進したものである。
階上の須弥壇(しゅみだん)上には中央に三門竣工と同時期頃の制作になる宝冠(ほうかん)釈迦如来像とその脇侍(きょうじ)である月蓋(がつがい)長者像(左)および善財童子(ぜんざいどうじ)像(右)が安置され、さらにその左右に十六羅漢像が並んでいる。
天井や上壁には狩野探幽(かのうたんゆう)·土佐徳悦の手になる華やかな鳳凰·飛天像が描かれている。
南禅寺見どころ2:大方丈

国宝
桃山時代(慶長16年移築)
南禅寺方丈は大方丈(おおほうじょう)および小方丈からなる。
大方丈は一重入母屋造、屋根は柿葺(こけらぶき)で、内陣のほか御昼の間·鳴瀧の間·麝香(じゃこう)の間など八つの部屋からなる。
小方丈は一重切妻造(背面)で前面は大方丈に接続し、屋根は柿葺で、虎の間03室からなる。
以心崇伝(いしんすうでん)の『本光国師(ほんこうこくし)日記」によれば、もとは慶長16年(1611)に内裏(だいり)の建物を移築したという。
各室には狩野永徳·宗秀山楽·光信·探幽など狩野一門によって壮麗な障壁画が描かれている。
南禅寺見どころ3:勅使門
重要文化財
桃山時代(寛永18年移築)
中門とならんで三門の正面に建つ総欅(けやき)造の四脚門で、屋根は切妻造で檜皮葺(ひわだぶき)である。
従来は内裏の紫宸殿(ししんでん)の東に位置する日華門(にっかもん)であつたとされていたが、慶長度に造営された内裏の日御門(ひのごもん)を下賜されて、寛永18年(1641)に移建したことが付属の棟札によってわかった。
正背面の上部の虹梁(こうりょう)や扉の上には、龍·麒麟(きりん)·孔雀·鶏などの動物や松·牡丹·雲·波などの彫刻を装飾性豊かにかざられ、いかにも桃山時代の志向を反映したものとなっている。
南禅寺見どころ4:琵琶湖疏水「水路閣」

南禅寺伽藍と亀山法皇の廟所南禅院との間に見えるレンガ造の建造物は水路閣と呼ばれ
る。
明治23年(1890)に竣工した琵琶湖疏水の支流で、木漏れ日に輝く秋の紅葉の季節は
ことのほか美しい。