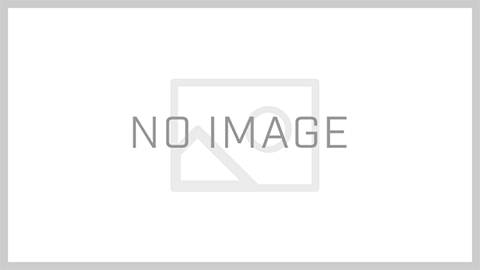法界寺 情報
住所: 京都府京都市伏見区日野西大道町19
TEL :075-571-0024
法界寺見どころまとめ
法界寺見どころ1:山門

江戸時代
がっしりとした本柱の後方に控柱2本を建て、切妻(きりづま)屋根をかけた薬医門(やくいもん)形式の山門。
西向きに建てられ、17世紀のものと推定されている。
門の奥にみえるのは阿弥陀堂。
法界寺見どころ2:阿弥陀堂

国宝
鎌倉時代
正面は7間、側面も7間の宝形造(ほうぎょうづくり)の阿弥陀堂。
頂上に宝珠をのせる屋根、その下に裳階(もこし)がつき、ともに槍皮葺(ひわだぶき)とする。
裳階の正面は、3間分を一段切り上げているので、軽快である。
このような仕様は平等院風風堂にもみられる。
法界寺見どころ3:阿弥陀如来坐像
国宝
平安時代
木造 漆箔 像高280.0cm
阿弥陀堂安置
腹前で定印(じょういん)を結んでゆったりと坐して膜想する阿弥陀如来像。
全体に円(まろ)やかな優しい気分が感じられる。
顔は頬の張りが豊かで、目鼻が小さいという特徴があるので童顔を思わせる。
衣文線は流麗で多めに刻む。
法界寺見どころ4:四天柱
重要文化財
鎌倉時代
板絵著色
各柱径54.0cm
四天柱は11段に珠文帯(じゅもんたい)で区切って、柱の四方に文様を描く段と、円相(えんそう)内の尊像を描く段を交互に配し、下から2段目は迦陵類伽(かりょうびんが)と宝相華団花文(ほうそうげだんかもん)が描かれている。
文様は中心の八葉蓮華を宝相華が円形に囲むもので、尊像は各柱16体で計64体が描かれる。
これらは金剛界受茶羅の三十七尊のうちの阿弥陀を除く三十六尊と、賢劫(けんごう)十六尊および十二天からなる。
図は前方西柱の8段目西側で金剛壁菩薩(こんごうまんぽさつ)。
法界寺見どころ5:小壁絵(東面)
重要文化財
鎌倉時代
主壁著色
各縦82.5cm 横147.0cm
各四天柱間の内法長押(うちのりなげし)の上は、3区に分かれた小壁(漆喰(しっくい)壁けとなり飛天が描かれる。
さらにその上の小壁には、笈形(おいがた)の唐草を描いている。
図は東面の3体の飛天のうちの2体で、斗(ます)や折上格天井の支輪板(しりんいた)にも蓮華や宝相華が描かれているのがわかる。
法界寺見どころ6:小壁絵(西面)
重要文化財
鎌倉時代
土壁著色
各縦82.5cm 横147.0cm
飛天図は東西面に各3体、南北面に各2体が描かれ、南面中央には雲上の火舎(かしゃ)と楽器、北面中央には楽器が、柱絵とは異なり自由な筆致で描かれる。
東·西面の飛天は作風を違えるが、共に阿弥陀如来の方向へ飛期する。
図は西面で、この左方飛天は後方を振り返りながらまるで背泳ぎのような姿態に表されている。
法界寺見どころ7:小壁絵 飛天(西面中央)
重要文化財
鎌倉時代
土壁著色 縦82.5cm 横147.0cm
西面の中央の飛天。
描線は速筆で肥痩があり、両手で持つ蓮華のたわみや、天衣の翻りなどによってスピード感が表現されている。
これらの表現は鎌倉時代の様式を示している。
上半身に衣をまとうのは珍しい。
法界寺見どころ8:薬師堂
室町時代(康正2年)
重要文化財
本尊の薬師如来像を記る、寄棟造(よせむねづくり)の重厚な建築で、阿弥陀堂の南に西向きで建つ。
正面は5間、 側面は4間で、四方に縁を廻らしている。
もとの薬師堂は阿弥陀堂の東方にあり、15世紀末頃に焼失したようだ。この堂は明治37年(1904)に大和龍田の伝燈寺の建物を移建したものである。
棟木の銘文から、康正2年(1456)に建てられたことが判明する。